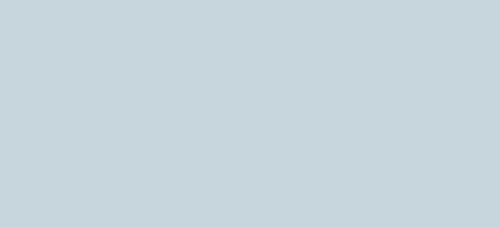夜の風に戦がれ、私は頭上の瞳を見上げた。
無知な観客に対して、神性・完璧を呈すると思わせるための演出であろうか、それは周囲に白く眩しい弧を描き、私に輪郭をなぞらせることを拒んだ。
私は少し眉を顰めた。知っているのだ。あれは神などではない。偽物だ。
神性は秘匿する行為から見出されるものであり、秘匿を行う演者そのものは神たり得ない。
なぜなら、神は完成されたものであり、秘匿に値する欠損を持っていない、故になにかを秘する必要がない。
完璧に近づこうとする未完成なものほど意識的に秘匿を必要とするのだ。
私はその傲慢な白い瞳に同族嫌悪と対抗心を燃やしながら、彼の歪な輪郭を捉えるため、つとめて目を凝らしてみる。
やがて画面を占領する白い輝きは私を圧倒し、突き刺し、畏縮させた。
今夜も先に目を逸らしたのはこちらだった。
そう、吾も彼のわざとらしい神性に魅せられた、所詮は観客のひとりであった。