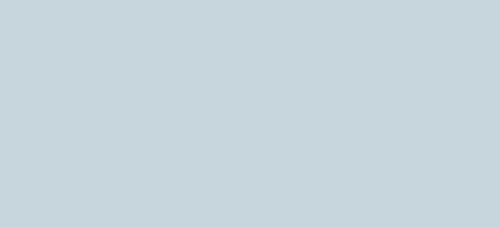胡乱な頭では昼食のメニューを決めることさえ億劫になる。
大学食堂にて、今日も私はカレーを選んだ。
カウンターの向こうの厨房で、調理師の女性がルーを慣れた手つきでよそう。彼女から配膳の完了したトレーを受け取り、席に戻ると、すでに向かい席に座した友人の塩屋澪が、日替わり定食のアジフライを満足げに頬張っていた。彼女はテーブルに置かれた私のトレーを一瞥し、眉をひそめる。
「なき、あんたって奴はまたカレーか」
「そうだけど……何か悪い?」
何を隠そう、私は安さと腹持ちの良さだけを理由に、ここ一年は昼食にカレーを選び続けている。断っておくが、これが特に好物というわけではない。
豊富なメニューの揃った食堂で毎日同じものを食べるなんて信じられない、とでも言わんばかりの驚愕と疑念を目に浮かべる澪に構わず、私は席に座った。
「もっと色々挑戦してみればいいのに」
「昼食のメニューごときに頭を悩ませたくないんだよ」
「たかだか昼食選びに何を悩むってのさ。それにさ、あたしが言いたいのはご飯のことだけじゃないの。華の大学生たるもの、新鮮な毎日を過ごすために少しでも新しい選択肢を取ってなんぼ!」
澪はそう言うと勢いよくご飯をかき込んだ。
今の時代に珍しい生命力みなぎる友人を前にして、私の脳内疲労はより深まってゆく。浮き彫りになるのは、メニュー選択の自由を放棄する程度に無気力で、刺激のない平穏な日常に身をやつし、将来の展望もなく、ただただ毎日を惰性で生きている自分。本来は、澪のようにリスクにとらわれない挑戦的な態度が年齢的にも社会的にも好ましくて、そんなことを言われるまでもなく、できることなら自発的にそういう人間でありたかった。だが哀しいかな、天地がひっくり返ろうが、今の私から澪のそれに準ずる瑞々しい衝動や欲求が湧き出ることはない。
表情から私の憂鬱を察したのか、澪はおもむろに食事の手を止めた。
「まったく、そんな顔されちゃ飯が不味くなるわ……。
あ、そうだ!これ見てよ」
澪は唐突に何かを思いついたようで、スマートフォンを手にして身を乗り出して来た。
「インカレの飲み会で紹介された彫師の人なんだけどさー」
眼前に差し出された携帯端末の画面には、「ロイコ」という人物のSNSアカウントが表示されていた。プロフィールの下側には、腕や肩の側面に描かれた繊細なタトゥーのイラストが連なっている。
一体どんなインカレサークルに所属すればタトゥーを生業にする人間と接点を持てるのかと訝しみつつ、彼女が持つ社交性に改めて舌を巻く。
タトゥーに関しては、裏社会の人間が自らの治安の悪さを露呈し周囲を威嚇するために施す身体装飾、という偏見的な知識しか持っていない。
「なにその微妙な顔は!今タトゥー流行ってるって知らないの?まぁいいや。んでね、来週の土曜日なんだけどね、あたしこのロイコって人のスタジオに予約入れたの!もーめっちゃ楽しみー!あ、ちなみに本物を入れるわけじゃなくてジャグアタトゥーっていうんだけどー……」
畳み掛ける澪の早口に戸惑いながら、私は「はあ」と気の抜けた返事をした。
澪が言うには、ジャグアタトゥーとはフェイクタトゥーの一種なのだそうだ。本物のタトゥーと違い施術時の痛みがなく、肌のターンオーバーと共に数週間で消えるためファッションとして気軽に楽しまれ、近年、若者の間で徐々に需要が高まってきているらしい。
いずれにせよ、ファッションなど自身の外見を利用した自己表現欲求がそれほど高くなく、万年ジーンズで過ごしている私のような人間にとっては到底関わりのない世界だ。冷ややかに、一線を引いた認識が変わることはない。
「で、それがどうしたの」
彼女の返答をなんとなく予測しながらそっけなく尋ねてみた。
すると澪は愛嬌のある丸い瞳を輝かせて、
「これ、なきも一緒に行かない?紹介割引で安くなるし。ね、いいでしょ!」
と言いながらこちらの目を見つめる。その圧に、私は思わず顔を背けた。
「あんたのことだから休日はずっと暇なんでしょ。たまにはなんか刺激入れないとさ、まだまだ若いのに老けちゃうぞ!」
余計なお世話以外の何者でもない…が、唯一無二の友人である澪の誘いがなければ、自室に引きこもり、特になにかを成すこともなく、その狭い空間でただただ無為に時間を消費するであろうということは紛れもなく事実である。
この私がタトゥーだなんて柄でもないが、皮膚に黒いインクを流し込むことを強く拒絶するような、乙女の如き徹底された処女性を持っているわけでもない。
拒否する理由がなくなり、私はしぶしぶ顔を縦に振る。主体性の低さを遺憾なく発揮する私は、澪の奔放な誘いに抗えきれず、粛々と流されていく。
今更悔いるまでもない。こんなやりとりはいつものことだ。
*
私は澪に連れられて街中の一角に建つ凡庸なビルの前に立っていた。
狭いエレベーターに乗り、六階で降りる。
無機質な廊下を進むと、ドアの横に設置されたアクリル看板「Studio Distoma」の文字が目に入る。目的のタトゥースタジオはこのドアの先にあるようだ。
初めて踏み入れる場所に緊張が止まず、澪の影に隠れるようにして室内に入ると、そこは意外にも、美容院のような雰囲気を醸し出した、薄暗く落ち着きのある店内だった。
澪が呼び鈴を鳴らすと、奥から袖の短い紺色の作務衣を着た男が姿を現した。
「や、予約入ってるお客サンかな?」
「はい、塩谷と浮夜です!」
澪が自分と私の苗字を告げると、男は蛇のような目を細めて笑顔を作った。妙に身体がこわばる。
「彫師のロイコです、今日はヨロシク。じゃ、どうぞこちらへ」
男は手短に挨拶をすませ、私と澪を客間へ案内した。二人でテーブルの前に置かれたソファーに座ると、資料を持ってきた男が対面の折りたたみ椅子に腰を下ろした。
そこで、まず施術内容の簡単な説明と、インクの原料に関するアレルギーの確認がなされた。
次に、デザインを決めるためのカウンセリングが始まった。
「さて、お二方はどんな絵を入れたい?」
そう言いながら卓上に資料を広げる男の右腕には、緑を基調にした地層のような縞模様と、先端に向かって濃度を増す黒点の連なりによって構成された、奇妙な柄のタトゥーがびっしりと掘り込まれている。それはトリックアートのように精密な規則性と不規則性を持ち、妖しげな蠢きを錯覚させた。私は本能的な抵抗感と好奇心が内側から湧き上がるのを感じながら、その物々しい腕から目を離せなくなっていた。
「あたし自分でデザインもってきたんですけど、こんな感じのアゲハ蝶入れたいです!」
澪はそう言って蝶が描かれた紙を鞄から取り出した。彼女は男の腕を気にする素振りなど一切見せず、無邪気にはしゃいでいる様子だった。
男は澪が希望するデザインの詳細と、タトゥーを入れる箇所の確認をすると、顔を上げて私の方を向いた。
「浮夜サンはどうする?」
蛇の瞳が私を捉える。私の身体は心臓を鷲掴みにされたかのように強張った。思考がよどんで、うまく言葉が出ない。
「ははっ、そんなに怖がらなくていいのに」
男は目を細めて、少し歪んだ口角を上げ、続けて語りかける。
「イメージが決まらないなら、こちらに『おまかせ』ってのもアリよ」
固まる私を見兼ねたのか、助言を呈された。私は生唾を飲み込み、ようやく言葉を絞り出す。
「なら、それで、おねがい、します」
「アンタ緊張しすぎでしょ!」
呑気に笑いながら澪が肩を小突いてきた。どうしてそんなに自然体でいられるのか。
「もーすみません、この子初めての場所に来るといつもこうで……」
母親のような澪の言葉に、男は苦笑いし、話題を戻す。
「本物のタトゥーでおまかせされると厳しいが、ジャグアならいずれ消えるからね。じゃ、浮夜サンは己の好きなように入れていいんだね?」
男がこちらを覗き込むようにして尋ねるので、私は視線を控えめに右下へずらして、無言で頷いた。
正直、今すぐこの空間から逃げ出したくてたまらなくなっていた。
男の目は心なしか、期待と喜びに満ちていた。
「オッケー、決まりだね。それじゃさっそく始めようか」
*
「なき……顔真っ青だけど大丈夫?」
私の背中をさする澪の声色は、普遍的な憂慮の中に少しの幻滅を含ませている気がした。
全ての施術が終わり、あの蛇のような男の巣窟……もとい、拠点からようやく解放された私は、遅れてやってきた膨大な疲労感に襲われ、憔悴しきっていた。
「ちょっと公園にでも寄って休憩しようか」
澪の提案に従い、彼女と共に街から少し外れた小さな公園に向かう。敷地内に設置されているベンチに二人で腰を下ろすと、澪はいつのまに自販機で購入したのか、「ほら」と言いながらミネラルウォーターの入ったペットボトルを私の手元に差し出した。
「あ……ありがとう」
過度の緊張で口の渇きが限界だったので、その気配りは本当にありがたく感じられた。
「お金はあとで返すね」
私は早速蓋を開け、中身を口に流し入れる。
「いやいいって!無理やり連れてきたあたしが悪いんだし。まさか、なきがあそこまで男の人が苦手だったなんて」
澪の一言に危うく口に含んでいた水を吹き出しそうになりそうになり、なんとか堪えた。
彼女の言う通り、自身に男性不信の気があることは否めないが、あの彫師に対する忌避感は相手が異性だからという単純明快な理由だけではないように思える。仮に女性だったとしても彼のことを好ましく思うことはないだろう。
「いやーごめん。でもロイコさんって結構イケてるわー。見た目もだけど腕もさ。ていうか、あの人数ヶ月前にスタジオ構えたばっかりらしいよ!あれは人気出るわー」
それなりの長い付き合いをしてきたから分かることだが、澪の鑑識眼は意外とあなどれない。特に、人を見る目に関しては光るものがある。
その能力はほぼ無意識的に働いているようで、一般化できる論理性は持たない。だが彼女が持つ豊富な経験によって裏づけられた高精度の直感は、一層優れた慧眼となって容易にダイヤの原石を探り出す。
実際、どうやってその存在自体を知るのかもわからない隠れた名店をいくつもピックアップしてきては、私を連れ回すということが過去に何度もあった。今回の件もその一つに加えられるか否かは、神のみぞ知るといったところだ。
さて、そんな彼女による「イケてる」との評を信じるならば、私が抱いた恐怖心は素人の観念が生み出した偏見の類に成り下がるわけだが、それはそれとして、彼への印象を今更、無理やり覆そうとしても簡単にはいかないというのが人の心情だ。
すると突然、澪が座ったまま身体を傾け、私の手元を凝視してきた。
「そういえば、なきがおまかせで入れてもらった柄ってどんなだったの?」
澪の指摘にはっとして、右腕の上着の袖をまくり手首の下側を露出させた。そこには薄く朧げになったタトゥーの柄が残っている。
「あーやっぱり、なきも洗ったばっかだから形わからんな」
私の腕を覗きこんだ澪が呟く。
彼女が言うように、ジャグアタトゥーはインクが乾いた後、流水で洗い流す必要がある。そこからインクが完全に発色するまで二十四時間以上かかるそうだ。よって、今自分の腕を見ても明瞭なタトゥーイラストを確認することはできない。
そんなことをしなくても、インクを流す前の記憶くらいあって当然だと思われるだろう。
しかし、信じがたいことに、どんなに頭を振り絞ろうが私のニューロンが正常に稼働することはなく、灰色によどんだ記憶ばかりが蘇る。
タトゥーの施術は数十分前に終わったばかりだというのに。カット編集を受けた動画のように、施術中の段落だけ不自然に切り落とされていて、その周辺をなぞろうとすると何も思い出せなくなる。こんなバカなことがあるだろうか。
額に脂汗を滲ませて俯く私に、澪がそっと語りかける。
「え……もしかして、忘れた?」
「……ごめん」
私の返答に、澪はさすがに笑いを堪えきれないといった様子で身体を震わせた。
「あっははは!記憶喪失するほど緊張する人初めて見るわ!なんだよー、めっちゃ気になるじゃん。浮き出たらあとでちゃんと写真送ってよね!SNSに載せるから」
なにやら強引に約束を取り付けられたようだが、今はそんな些細なことに構う余裕などない。
呑気に笑い飛ばす澪を尻目に、直前に執り行われた施術の記憶が一切ないという明確な異常事態を前にした私は、ただ独り、不吉な予感をふつふつと募らせるばかりだった。
******
たゆたう脳内は、この白い世界を意味もなく眺めている。
夢か、幻か。
確実に言えることは…
閉じられた瞼の向こう側を意識できるほど、肉体は鮮烈で浅い世界に閉じ込められている。
ただ、それだけだった。
仰臥する私の足元に、白い着物の女が佇んでいる。
いつの間に現れたのか。
やがて彼女はゆっくりと前へ進み、私の身体に覆い被さるように四肢を広げて乗り込んできた。
鼻の先で、女の縮れた黒髪が揺れる。その時、視線以外の自由が奪われ、私の体は硬直する。
暗がりの中、既視感のある鋭利な瞳孔がこちらを見下ろしている。
冷たいミミズが全身を這い回っているような寒気がして、もがこうとするが、強固な金縛りを受けた身体はびくともしない。
「ああ、お前の肌は具合がいい」
わずかにノイズを纏わせた、低くて艶のある女の声が鼓膜を揺らす。
「不純物が適度に混じった白い肉体。ここまで活きの良いデコイは初めてだ」
不純?デコイ?何の話だろう
「あの器もまあ、悪くはなかったが」
ぬるい汗が首を滑り落ちる。
「やはり雄を媒体とするには何かと都合が悪い」
眼前に迫った女の顔には、不愉快な愉快がべっとりと貼り付けられている。
目を背けることすらできない。
「これは己たちにとっては生存戦略の一環に過ぎないが、ヒトという種はそこにそれ以上の何かを求めるものだろう?」
その顔を私の耳に近づけ、囁く。
「だから、これは己なりの愛ということだ」
「よろこべ」という言葉と共に、その鋭い牙を私の首筋にさくり、と立てた。
食い込むほどにじわじわと込み上げる痛み、恐怖、焦り、怒り、すべてがごちゃ混ぜになりながら、その隙間でひそかに思考は冴えていく。
なんとしてでもこの倒錯した存在から逃れなければならない。強力な思念が、熱が、脳を占領する。
仕掛けられた精神的拘束を、力任せに引きちぎる。脳が焼けるように熱くなる。それと同時に、私の右側頭部から刀剣のような平たく細長い角がにゅるりと現れた。
私はこれを好機と捉え、そのまま頭を斜め上に振りかぶり、上に被さっている女の頸動脈付近を力任せに何度も何度も貫く。
女は抵抗することなく、物も言わず、なされるがまま、私の愚鈍な斬撃を存分に受け続けた。血飛沫の代わりに、粘性の高い透明な液体があたり一面に飛び散っていく。顔を覆うように乱れる黒髪から、歪んだ口端が垣間見える。私はただただ、一心不乱に刺し続けた。
やがて、「パン」という乾いた音がした。
複雑に裂傷した女の首筋から、米粒のような白い卵が大量に溢れ出す。
私はその光景を見て、安堵する。
ああ、やっと終わった。
薄れゆく意識と共にその場に倒れ落ちていく……
******
カーテンの隙間から差し込む日の光に照らされて、右腕の奇妙な紋様が蠢いていた。
異様な清々しさに、吐き気を催しそうになる。
脳内のストレージを大きく占領していた『胡乱』が、全て強制的に溶かされ、型に流し込まれ、一晩で冷やされたようだ。
何もかもがひとつになったようで、明らかに異様の何かが隣に在る。
彼の声が示すことには、己の名は「ナギ」というらしい。