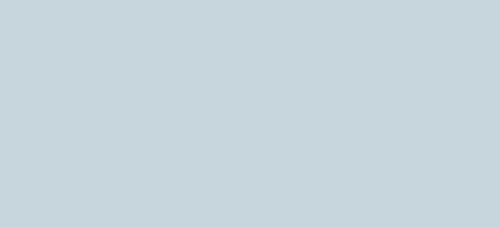或る夜。満点の星空。
肺を突き刺すほど澄み渡る空気の中、一人の女が佇んでいた。
女は、巻き貝型の煙管を携え、火も点けずに呑んでいる。大胆に管から漏れ出る膜、もとい煙たち。彼らはまるで生命を伴うかのように、無邪気に女の周囲をただよう。
やがて女は顔を上げ、天球の光に臨んだ。
程よく主張するマイナス12.7等星の光は、観客の視力を奪うような威力は持たないが、その印象的な姿形を網膜に焼き付けられた見物人の心は、遅効性の毒を仰いだ人体の如く、じわりじわりと圧倒されていく。
しかし、女はただ圧倒されるのみに終わらず。澄みきった夜の神秘をその身に宿して、天球が及ぼした戦慄の味でさえ舌で転がし、ひそかに歓迎するのだろう。
女は目を閉じ、その光の先にある天体の輪郭をなぞり始めた。
彼女の意識は、天体の裏側にある目的地の座標を指定し、移転を目指して煙のようにゆっくりと立ち上る。
通常、その天体は守秘義務を遵守し、我々には決して裏の顔を見せない。しかし彼女の遠隔透視にその原始的な秘匿行為は通用しないのだ。
複雑に単純化された透明な意識『タマ』は、世界の縮図である夢海の中を漂っている。形而上の世界を漂うタマにとって、全ての物理的な障壁は障壁足り得ない。タマは宿主の操縦を受け、往来を繰り返しながら迫り来る潮流を乗りこなし、目的地を目指して旋回を繰り返し、進んでいく。
そして、女は天体の内側で目を覚ました。