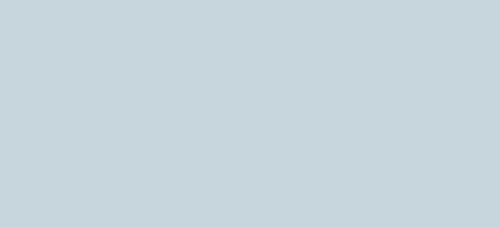窓から差し込む自然光と、丸太の暖色が温もりをもたらすログハウス。
滑り台やジャングルジム、ブランコなどさまざまなアスレチックが置かれている。小さな棚で区画されたスペースには、広めのローテーブルに折り紙やお絵描き用の画用紙、クレヨンが用意されている。
しかし、それらと戯れる幼児の姿などは見当たらない。管理人や保護者の陰もない。児童向けの施設としては、似つかわしくない静けさが広がっている。
その静けさの中、わたしはぽつりとたたずんでいた。
キッズスペースの利用対象年齢に当たるわたしは、眼前に広がるポップな遊具の群に魅了されるような瑞々しい童心を忘れたわけではなかったが、何よりも興味を持っているのは足元の床板……正確に言うと、床板を隔てた向こう側にある地下空間だった。
地下への入り口は簡単に見つかる。遊具が置かれたスペースからは少し離れた部屋の一角に、子ども一人がやっと通れるような正方形の穴が空いていて、側面には木製の梯子が掛かっている。
それを目にしたわたしは、居ても立っても居られなくなり、穴に近づいて、梯子に足を掛けた。
最後の踏み桟から足を離し、ゆっくりと降り立つ。触れた素足から伝わるコンクリートの冷たさが、異世界への到達を知らせる。
現れたのは人工的で寂しげな床の薄水色、規則的に並んだ照明と太い支柱、無限に続く地下通路。今、有機的に呼吸を続けていられるのが不思議に思えるほどに、視界は無機質な郷愁と薄暗い安寧に満ち満ちている。
当て所もなく、ただただ前へ歩いていく。
細胞分裂で生まれたような壁が、柱が、照明が、どこまでもくり返して流れていく。
ふと、足首ほどの高さに水が張られていることに気づいた。プール水の塩素のような匂いが鼻につく。足元にまとわりつく液体のなまあたたかさが少しく不愉快だが、かまうことはない。そのまま歩いていく。
水かさはゆっくりと増えていき、やがて膝をかぶるほどになり、ついには全身が覆われた。浮力が働くことはなかった。地面から離れることなく、足取りは変わらず歩いてゆき、呼吸も難なく続いていく。
水中にて、無限空間の開放感は失われていく。進むほどに双方の壁が狭まっていく……
行き止まりを想像させる展開に不安を覚える暇もなく、前方に現れたのは、小さな石段だった。